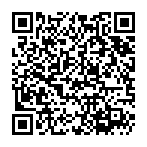日本の対外戦争
残念ながら決して褒められた歴史ではない。
特に文明開化(1868年)以降は
神道の国教化に始まり、
富国強兵策による悲惨な歴史の張本人となっている。
よって、これを踏まえて、
21世紀に生きる我々は、世界に対して、
常に謙虚に謙虚に振る舞う必要がある。
特に”自省心”の極めて低い日本人が、
未だに、神社祭禮・神社詣でをしている事実に
驚愕させられる。
更に、地域に氏子集団を形成し
そこから国家及び地域自治に、
飼いならしたお抱え議員を出す仕組みが
厳然と機能していることにも
唖然とさせられる。
(サイト・マスタ)
古代~中世
1. 白村江の戦い(663年)
原因:日本(倭)が、滅亡寸前の百済を支援するために出兵した。
背景:唐と新羅が同盟し、百済を滅ぼそうとした。百済と友好関係にあった日本は介入するも、唐・新羅の連合軍に敗北。
2. 元寇(1274年・1281年)
原因:モンゴル帝国(元)が日本を属国化しようとした。
背景:元は朝鮮半島(高麗)を支配し、日本に朝貢を求めたが、日本(鎌倉幕府)が拒否。これに対し、元は日本侵攻を決定。
近世(戦国~江戸時代)
3. 文禄・慶長の役(1592年~1598年)
原因:豊臣秀吉が「明征服」を目指し、その通過地点として朝鮮半島に侵攻した。
背景:秀吉の大陸進出構想があったが、朝鮮(李氏朝鮮)が拒否したため、日本軍が出兵。明も介入し、日本は撤退。
近代(幕末~昭和初期)
4. 薩英戦争(1863年)
原因:生麦事件(薩摩藩士がイギリス人を殺害)に対する報復。
背景:イギリスは薩摩藩に賠償を求めたが、薩摩藩は拒否。イギリス艦隊が鹿児島を砲撃し、戦闘に発展。
5. 下関戦争(1864年)
原因:長州藩が外国船を砲撃したため、報復を受けた。
背景:長州藩は尊王攘夷を掲げ、関門海峡を通る外国船を攻撃。イギリス・フランス・オランダ・アメリカの連合艦隊が報復攻撃。
6. 台湾出兵(1874年)
原因:台湾の原住民が琉球人を殺害したため、日本が報復出兵。
背景:日本は琉球王国を自国の一部と考えており、事件を理由に台湾へ軍を派遣。清と交渉し、一部要求を認めさせる。
7. 日清戦争(1894年~1895年)
原因:朝鮮の支配権を巡る日本と清の対立。
背景:朝鮮で甲午農民戦争(東学党の乱)が発生し、日本と清が軍を派遣。日本は朝鮮を自国の影響下に置こうとし、戦争に発展。
8. 北清事変(1900年)
原因:中国の反外国運動「義和団の乱」に対処するため。
背景:義和団(清の排外主義運動)が外国人を攻撃。日本を含む列強が連合軍を派遣し、北京を占領。
9. 日露戦争(1904年~1905年)
原因:ロシアと満州・朝鮮の支配権を巡って対立。
背景:ロシアは満州・朝鮮への進出を進め、日本はロシアの南下を警戒。外交交渉が決裂し、日本が開戦。
10. シベリア出兵(1918年~1922年)
原因:ロシア革命後の混乱に介入し、共産勢力(赤軍)の影響拡大を防ぐため。
背景:日本はロシアの反革命勢力を支援し、資源獲得も狙い出兵。しかし、戦局が悪化し撤退。
11. 満州事変(1931年)
原因:関東軍が満州を支配するため、自作自演で中国軍の攻撃をでっち上げた。
背景:満州における日本の権益拡大を狙い、柳条湖事件を起こし、満州を占領。国際的非難を受けたが、日本は満州国を建国。
12. 日中戦争(1937年~1945年)
原因:盧溝橋事件(日中両軍の衝突)をきっかけに全面戦争へ。
背景:日本は中国の支配を強めようとし、中国側が抵抗。泥沼化し、太平洋戦争と並行して戦うことに。
13. 太平洋戦争(1941年~1945年)
原因:アメリカの経済制裁により、日本が資源確保のため開戦。
背景:日本は中国戦線を維持するため東南アジアの資源を狙ったが、アメリカが石油禁輸を決定。これに対し、日本はハワイの真珠湾を奇襲し、戦争開始。
ChatGptより
他にも、韓国併合(1910年)があるが、戦争ではないので、ここでは割愛します。
2025.2.19現在
近代日本の宗教政策
近代日本の宗教政策は、明治維新(1868年)以降、大きく変化しながら展開されました。以下の主要な流れを説明します。
1. 明治維新と神道の国教化(1868年~)
明治政府は天皇を中心とした国家体制を確立するため、神道を国教化する政策を推進しました。
①神仏分離令(1868年):仏教と神道を分離し、仏教勢力を抑制。廃仏毀釈運動が全国で発生。
②大教宣布の詔(1870年):神道を中心とした国民教化を進める政策が打ち出される。
2. 宗教の自由と統制(1889年~)
**大日本帝国憲法(1889年)**により、「信教の自由」が一定程度認められる(ただし「安寧秩序を害しない限り」という制約付き)。
**宗教団体法(1899年)**により、仏教・キリスト教などの宗教団体は政府の管理下に置かれる。
3. 国家神道の確立(1890年~1945年)
**教育勅語(1890年)**によって、忠君愛国思想が強調され、神道が国民道徳の基盤となる。
神社は宗教ではなく国家儀礼の場と位置づけられ、事実上の「国家神道」となる。
弾圧政策:大本教などの新宗教が弾圧を受け、日蓮主義を唱えた**創価教育学会(後の創価学会)**も戦時中に弾圧される。
4. 戦後の宗教改革(1945年~)
GHQによる政教分離政策(1945年):国家神道は解体され、神社は宗教法人となる。
**日本国憲法(1947年)**により、完全な信教の自由が保障される。
その後、新宗教(創価学会、立正佼成会、天理教など)が発展。
まとめ
近代日本の宗教政策は、
① 明治初期の神道国教化、
② 大日本帝国憲法下での一定の信教の自由、
③ 国家神道による統制と弾圧、
④ 戦後の政教分離と自由の拡大
2025.2.22現在
 日めくり人間革命
日めくり人間革命