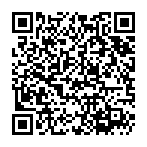新・人間革命1巻
旭日
2020年11月1日
第1696回
幸福と平和
<あらゆるものが共有する目的>
人生の目的──それは、幸福。
人生の願望──それは、平和。
その幸福と平和に向かって、
歴史は展開されていかねばならない。
人間は、
その確かなる軌道の法則を、
追求する生き物である。
科学も、政治も、社会も、宗教も、
目的はこの一点にあらねばならない。
<新・人間革命> 第1巻 旭日 15頁
2023.9.9整理
2021年10月8日
第1737回
世界広布にあたって
一番恐れていること
<「随方毘尼」が重要!>
伸一は笑いながら、清原に言った。
「清原さん、ここは日本じゃないんだよ。ハワイにはハワイの風俗や習慣があるんだから、それを尊重することだよ。日本とは気候も文化も違うのに、学会では、日本と同じ服装やヘアスタイルでなければいけないなんて言われたら、みんな信心するのがいやになってしまうよ。まるで、戦時中の国防婦人会みたいでさ。そんなことは御書にも書かれていないし、仏法の本義とは違うんだから、それぞれの良識に任せ、自然なかたちでいいんだよ。
ましてや、今日のような座談会では、みんなの悩みや疑問をよく聞いて、納得できるように、的確に指導し、励ましていくことが主眼になる。そのためには、自由で和やかな、どんなことでも話せる雰囲気をつくることが大事なんだ。だから、みんなにも気楽な服装で来てもらって、こちらも、それに合わせていくべきだね」
清原は、自分の考えの浅さを恥じた。
「そうですね。私、みんなに変なこと言わないでよかったわ。でも先生、私はムームーなんて持ってきていないんです」
「わかっているよ。いいよ、その格好で」
笑いが広がった。
すると、十条潔が口を開いた。
「風俗や習慣の違いというのは、確かに大きな問題ですね。先生、私は、勤行の時の正座も、外国人にはかなり苦しいのではないかと思うんです。しかも、アメリカの家はたいてい木の床ですから……。でも、これは変えるわけにはいかんのでしょうね」
伸一は即座に答えた。
「いや、当然、椅子に座って勤行をすることも検討しなければならないだろう。正座の習慣がない人たちにとっては、拷問に等しい苦痛だもの。それでは、勤行しても歓喜なんかわかないよ。だから、仏法には随方毘尼という考え方がある。御本尊への信仰という、大聖人の仏法の本義に違わない限り、化儀などは各地の風俗や習慣、時代の風習に従ってもいいんだよ」
「なるほど……。これからのことを思うと、もっと柔軟に物事を考えていかないといけませんね」
「私が一番恐れているのは、
日本でやってきたことを絶対視して、
世界でもすべて同じようにしなければならない
という考え方に、幹部が陥ることだ。
それでは、世界の人たちに、
日本の民族衣装を無理やり着せるようなものだ。
そして、そうすることが
正しい信心の在り方のように思ったりしたら、
仏法を極めて偏狭なものにしてしまうことになる。
そうなれば、仏法というより、
”日本教”になってしまう。
大聖人の仏法は、
日本人のためだけの教えではなく、
全世界の人類のための宗教なんだからね」
伸一は、戸田城聖に、世界の広宣流布を使命として託された日から、やがて、海外で直面するであろう諸問題について思いをめぐらし、その一つ一つについて、熟慮に熟慮を重ねてきたのである。風俗や習慣の違いに対して、どう対応していくかということも、彼のなかで、検討し尽くされてきた問題であった。彼の胸中には、既に世界広布の壮大にして精緻な未来図が、鮮やかに描かれていたのである。しかし、それを知るものは誰もいなかった。
<新・人間革命> 第1巻 旭日 43頁~45頁
2023.9.9整理
2021年10月5日
第1734回
本当の学会の組織
<自分の力で一からつくる>
伸一は、ハラダに笑顔を向けた。
「ええ、ハワイ島に帰る飛行機の時間ですので」
「そうか。君のことは生涯忘れません。
ところで、君にも男子部の班長になってもらおうと思うんだけど、いいかい?」
「はい……」
「日本で班長といえば百人ぐらいの部員がいるが、
君には一人もいないことになる。
でも、班長は班長です。
その自覚で、
君が自分の力で班をつくっていくんだよ。
それが本当の学会の組織なんだ。
戸田先生は
『青年よ、一人立て!
二人は必ず立たん、
三人はまた続くであろう』と言われている。
その精神で戦うのが学会の真実の青年です。
これから君が、
どういう戦いをし、どう生きていくのか、
私は、十年先、二十年先、三十年先まで、
じっと見ていきます。
勝とうよ、人生に。
絶対に自分に負けないで、私に付いてくるんだよ」
<新・人間革命> 第1巻 旭日 68頁~69頁
2023.9.9整理
2021年10月4日
第1733回
社会的な信頼を得るためには
<仕事で成功すること>
伸一は、
生活の問題から組織運営の在り方にいたるまで、
あらゆる面からアドバイスしていった。
「リキさん、
社会的な信頼を得るために、
まず大切なのは、
仕事で成功することです。
それがいっさいの基盤になる。
そのために、
人一倍、努力するのは当然です。
そして、題目を唱え抜いて、
智慧を働かせていくんです。
広宣流布をわが人生の目的とし、
そのために実証を示そうと、
仕事の成功を祈る時に、
おのずから勝利の道、
福運の道が開かれていきます」
<新・人間革命> 第1巻 旭日 75頁~76頁
2023.9.9整理
2025.2.8整理
2021年10月6日
第1735回
みんなのために戦うリーダー
「これからの人生は、
地区部長として、私とともに、
みんなの幸せのために生きてください。
社会の人は、
自分や家族の幸せを考えて生きるだけで精いっぱいです。
そのなかで、
自ら多くの悩みを抱えながら、
友のため、法のため、広布のために生きることは、
確かに大変なことといえます。
しかし、実は、
みんなのために悩み、祈り、
戦っていること自体が、
既に自分の境涯を乗り越え、
偉大なる人間革命の突破口を開いている証拠なんです。
また、
組織というのは、
中心者の一念で、
どのようにも変わっていきます。
常にみんなのために戦うリーダーには、
人は付いてきます。
しかし、目的が自分の名聞名利であれば、
いつか人びとはその本質を見抜き、
付いてこなくなります」
<新・人間革命> 第1巻 旭日 76頁~77頁
2023.9.9整理
2025.2.8整理
2021年10月7日
第1736回
人の育成
渾身の力を振り絞らずして、
人の育成はできない。
生命から発する
真心と情熱のほとばしりのみが、
人間を触発し、人間を育む。
<新・人間革命> 第1巻 旭日 77頁
2023.9.9整理
新世界
2021年10月9日
第1738回
政治と宗教は次元が違う
<学会にも多様な考えがあってよい>
伸一は、笑みをたたえて言った。
「それで、君は安保に対して反対なのか、それとも賛成なのか?」
「私は断固反対です。安保は廃棄し、中立の立場に立つべきだと思います」
すると、別の青年が発言した。
「私は、全面的に賛成とはいいかねますが、今のところ、やむをえないと思います。日本は、アメリカの協力なくしては、軍事的にも、経済的にも、独り立ちはできない状況です。今、安保を廃棄したりすれば、日本はアメリカを敵に回すことになります。したがって、安保を今の段階で廃棄せよというのは、現実を無視した意見です」
ほかの青年たちも意見を述べたが、
主張は二つにわかれた。
伸一は、彼らを包むように見回すと、
にこやかに語り始めた。
「青年部の君たちの間でも、
これだけ意見が食い違う。
一口に学会員といっても、
安保に対する考え方はさまざまだよ。
反対も賛成もいる。
そして、
どちらの選択にも一長一短がある。
それを、
学会としてこうすべきだとは言えません。
私はできる限り、みんなの意見を尊重したい。
大聖人の御書に、
安保について説かれているわけではないから、
学会にも、
いろいろな考えがあってよいのではないだろうか。
政治と宗教は次元が違う。
宗教の第一の使命は、
いっさいの基盤となる人間の生命の開拓にある。
宗教団体である学会が、
政治上の一つ一つの問題について見解を出すのではなく、
学会推薦の参議院議員がいるのだから、
その同志を信頼し、どうするかは任せたいと思う。
ただし、
政治上の問題であっても、
これを許せば、
間違いなく民衆が不幸になる、
人類の平和が破壊されてしまうといった
根源の問題であれば、
私も発言します。
いや、先頭に立って戦います」
青年たちの目が光った。
<新・人間革命> 第1巻 新世界 99頁~101頁
2023.9.9整理
2025.2.8整理
2021年10月16日
第1745回
一瞬の時を生かす
伸一は、こうした一瞬一瞬の時を、決して疎かにはしなかった。戦いの勝敗も、いかに一瞬の時を生かすかにかかっている。友への励ましにも、逃してはならない「時」がある。
彼の反応は常に素早かった。時を外さず、いつも機敏に手を打った。それは、「今」を逸すれば、永遠にそのチャンスをなくしてしまうかもしれないという、会長としての緊迫した責任の一念が培った、感受性の鋭さであったといえるかもしれない。更には、青春のすべてを注いで戸田城聖に仕え、後継の弟子として彼が受けた厳しい訓練のなかで、体で習得していったものでもあった。
<新・人間革命> 第1巻 新世界 114頁
2021年10月10日
第1739回
学会と社会の間に垣根なし
<学会理解者を大切に>
伸一は、同行のメンバーの気持ちを察して、すかさず言った。
「私は、ポールさんのような方を大切にしたいんです。信心をしていないのに、学会をよく理解し、協力してくれる。これほどありがたいことはない。私は、その尽力に、最大の敬意を表したいんです。みんなは、ただ信心しているか、していないかで人を見て、安心したり、不安がったりする。しかし、それは間違いです。その考え方は仏法ではありません。
信心はしていなくとも、人格的にも立派な人はたくさんいる。そうした人たちの生き方を見ると、そこには、仏法の在り方に相通じるものがある。また、逆に信心はしていても、同志や社会に迷惑をかけ、学会を裏切っていく人もいます。だから、信心をしているから良い人であり、していないから悪い人だなどというとらえ方をすれば、大変な誤りを犯してしまうことになる。いや、人権問題でさえあると私は思っているんです」
伸一の思考のなかには、学会と社会の間の垣根はなかった。仏法即社会である限り、仏法者として願うべきは、万人の幸福であり、世界の平和である。また、たとえば広い裾野をもつ大山は容易に崩れないが、断崖絶壁はもろく、崩れやすいものだ。同様に、盤石な広布の建設のためには、大山の裾野のように、社会のさまざまな立場で、周囲から学会を支援してくれる人びとの存在が大切になってくる。更に、そうした友の存在こそが、人間のための宗教としての正しさの証明にほかならないことを、彼は痛感していたのである。
<新・人間革命> 第1巻 新世界 118頁~119頁
2021年10月12日
第1741回
アメリカ同志の誓いの「三指針」
伸一は額に噴き出た汗を拭うと、力強い声で語った。
「皆さんは、使命あってこのサンフランシスコに来られた。今は、それぞれ大きな悩みをかかえ、日々苦闘されていることと思いますが、それはすべて、仏法の偉大なる功力を証明するためにほかなりません。
皆さんこそ、アメリカの広宣流布の偉大なる先駆者です。皆さんの双肩には、未来のアメリカのいっさいがかかっていることを、知っていただきたいのです。
その意味から、私は、本日、三つのことをお願いしておきたいと思います。まず、
第一に、市民権を取り、良きアメリカ市民になっていただきたい、ということです。広宣流布といっても、それを推進する人びとが、周囲からどれだけ信頼されているか、信用を得ているかによって決まってしまう。アメリカにいながら、自分のいる国を愛することもできず、日本に帰ることばかりを考え、根無し草のような生活をしていれば、社会の信頼を得ることはできません。市民権を取るということは、国を担う義務と責任、そして、権利を得ることです。それが社会に信頼の根を張る第一歩になっていきます。
第二には、自動車の運転免許を取るようにお願いしたい。アメリカは日本と違って国土も広い。どこへ行くにも車が必要です。皆さんが動いた分だけ、広宣流布が広がってゆくことを思うと、ドライバーのライセンスの取得は、広布の本格的な戦いを開始するうえで、不可欠な条件といえます。
第三に、英語をマスターしていただきたい。自由に英語を話せるようになれば、アメリカ人の友人も増え、多くの人と意思の疎通が図れます。弘教は人との交流から始まり、交流は対話から始まります。また、大聖人の仏法は、日本人のためだけのものではありません。アメリカの広布を考えるならば、やがて座談会も、会合での指導も、英語で行われるようにならなければならない。その中心者となっていくのが、ここにいらっしゃる皆さんです。したがって、たとえば日本の『かぐや姫』の話を、英語でしてあげられるぐらいの力を、まず身につけていただきたい」
伸一は、場内を見渡した。静かに頷いている人もいれば、当惑ぎみの表情をしている人もいた。また、隣同士で顔を見合わす婦人もいる。互いに相手が車を運転し、英語を自在に操る姿など、想像もできなかったのであろう。
彼は、メンバーの思いを察知し、言葉を継いだ。
「大変なことを要求しているように思われるかもしれませんが、アメリカの広布を担うのは、皆さん方しかいません。ご婦人の皆さんのなかには、車を運転したり、英語を自在に操るなんて、とても自分には無理であると思っている方もおられるでしょう。
しかし、まず〝必ずできる〟〝やるぞ〟と決めて挑戦し、努力してみてください。皆さんならできます。アメリカには、女性ドライバーは、たくさんいるではありませんか。女性でも車を運転するのは、アメリカでは常識です。やがて日本だって十年もすれば、そんな時代になります。その意味でも、皆さんは日本女性の先駆者となっていただきたいんです。
また、英語だって、できないわけがありません。ここでは五歳の子どもだって、英語を話している。英語に比べれば、日本語は漢字もあり、大変に難しいといわれています。でも、皆さんは、その日本語を見事にマスターしているではないですか」
笑いが起こった。その笑いが皆の心にのしかかっていた重さを吹き払い、希望を芽吹かさせた。
”そうだ。やってできないことはない!”
皆、そんな気がしてくるのだった。
この三つの指針を、伸一は海外訪問の期間中、各地の座談会で訴えていった。やがて、それは、アメリカの同志の誓いの「三指針」となっていったのである。
<新・人間革命> 第1巻 新世界 124頁~127頁
2021年10月13日
第1742回
金銭問題
山本伸一が別室に引き上げて間もなく、婦人部長の清原かつがやって来た。
「先生……」
清原は言いにくそうに、伸一に告げた。
「実は、ユキコ・ギルモアさんたちが、これから、私たちに食事をご馳走しようとして、みんなから一ドルずつ、お金を集めたということなんですが……」
清原の話を聞くと、伸一は顔を曇らせた。
「それはいけない!」
彼は、ユキコ・ギルモアを呼んだ。そして、諄々と指導した。
「あなたたちの気持ちは嬉しいし、ありがたい。しかし、皆、生活も大変なはずです。私たちのことで、みんなに余計な負担をかけるようなことをしてはならないし、そんな必要はありません。また、私に食事を振る舞うために、お金を集めることにしたと言われれば、たとえ不本意であっても、従わざるをえない雰囲気がつくられてしまいます。そうなれば、みんなの意思とはいっても、半ば強制のようになり、それによって、学会に不信をいだく人もいるかもしれない。発意は真心であっても、結果としては、みんなの信心を混乱させることになりかねません。
ですから、幹部は、会員から不用意にお金を集めるようなことは慎まなければなりません。学会では、お金の扱いについては、神経質なぐらい厳格にしているんです。厳しいことをいうようですが、集めたお金は、あなたから、一人ひとりに訳を説明して、丁重にお返ししてください」
ギルモアは、最初は、伸一の指摘に戸惑いを覚えたようであったが、申し訳なさそうに、「わかりました」と言って、部屋を出ていった。
彼女の善意から発した行為であることは、伸一にもよくわかった。それだけに、みんなに頭を下げて、お金を返すことを思うと、かわいそうな気もした。しかし、地区部長として組織を運営していくには、学会の金銭の取り扱いの厳格さを身につけなければ、いつか、金銭の問題で失敗しないとも限らない。それは、同志を思うがゆえの慈愛の指導であった。
<新・人間革命> 第1巻 新世界 130頁~131頁
2021年10月11日
第1740回
人びとの悲しみ、苦しみを、
誰よりもよく知っている人こそ人材
<同志を見下すな>
その時、理事の石川幸男が、傍らに来て座った。
「こうして見てますと、地区を結成しても心配ですな。幹部になった者も含め、とにかく常識がないし、物事を知らなすぎる。これで果たしてやっていけるんですかね。本当に人材がおりませんな」
同志を見下げたような口調であった。伸一は憮然としながら答えた。
「私は、決してそうは思いません。みんな人材です。これから光ってゆきます。純粋に信心を全うしていけば、みんな広布の歴史に名を残すパイオニアの人たちです。未来が楽しみです」
石川は「ほう」と言って部屋を出ていった。
この日、幹部に登用した人たちは、確かに幹部としての経験にも乏しく、未訓練であることは間違いなかった。
また、社会的な立場や肩書も、決して立派とはいえなかった。
しかし、アメリカという異国にあって、苦労に苦労を重ねながら、信心に励んできたメンバーがほとんどである。
人びとの悲しみ、苦しみを、誰よりもよく知っている。
そうであるなら、広宣流布という人間の一大叙事詩をつづるリーダーとして、最もふさわしい、尊い使命をもった人たちといわねばならない。
伸一には、一人ひとりが、やがて、キラキラと七彩の輝きを放つ、ダイヤモンドの原石のように思えてならなかった。
<新・人間革命> 第1巻 新世界 132頁~133頁
錦秋
2021年10月21日
第1751回
先生の思い
<陰の人として同志のために尽くすこと>
カメラを手にした、若い婦人から声があがった。
「先生、記念撮影をしてください」
「撮りましょう。
せっかく、皆さんが来てくださったんですから」
伸一を中心にして、皆が並ぼうとすると、
彼は、さっと後ろに退いた。
皆、怪訝な顔で伸一を見た。
「皆さんが前に来てください。
私は後ろでいいんです。
後ろから皆さんを見守っていきたいんです」
それは、伸一の率直な気持ちであった。
会長として広宣流布の指揮をとることは当然だが、
彼の思いは、
常に陰の人として同志のために尽くすことにあった。
伸一の言葉に、メンバーは驚きを隠せなかった。
皆がいだいていた「会長」のイメージとは、
大きく異なっていたからである。
伸一の態度は、
およそ世間の指導者の権威的な振る舞いとは正反対であり、
ざっくばらんで、
しかも人間の温かさと誠実さが滲み出ていた。
<新・人間革命> 第1巻 錦秋 143~144頁
2023.9.9整理
2021年10月15日
第1744回
まことの対話
メンバーが伸一の部屋に入ると、そこは、さながら座談会場のようになってしまった。
メンバーは、それぞれ伸一に自己紹介し、近況を報告していった。皆、彼の来訪を待ちわびていた人たちである。話しながら感極まって泣きだす人もいた。
伸一は、一人ひとりの話を聞き終わると言った。
「さあ、せっかくの懇談の機会ですから、どんなことでも、聞きたいことがあったら聞いてください」
メンバーは、この機会を待っていたかのように次々と質問をぶつけた。仕事の悩みもあれば、病気の問題もあった。
一人のアメリカ人の壮年からは、英字で表記した経本をつくってほしいとの、要望が出された。それまで英字の経本がなかったために、日本語がわからないメンバーは、人の勤行を聞いて、耳で覚えるしかなかったのである。
「わかりました。それはお困りでしょう。すぐに検討します」
伸一は帰国後、直ちにこれを進めていった。
彼は、どこにあっても、常に同志との率直な語らいを心がけた。その対話のなかから人びとの心をつかみ、要望を引き出し、前進のための問題点を探り当てていったのである。そして、問題解決のために迅速に手を打った。提起された問題が難題である場合には、何日も考え、悩んで、なかなか寝つけないことも少なくなかった。
まことの対話には、同苦があり、和気があり、共感がある。対話を忘れた指導者は、権威主義、官僚主義へと堕していくことを知らねばならない。
伸一の思いは、いつも広宣流布の第一線で苦闘する同志とともにあった。いな、彼自身が最前線を駆け巡る若き闘将であったといってよい。
<新・人間革命> 第1巻 錦秋 145頁~146頁
2021年10月20日
第1750回
使命の目覚め
<人間性の光彩とは、利他の行動の輝きにある>
伸一は、婦人の持ってきたテープレコーダーを見て言った。
「ありがとう。嬉しいね。同志のことを考えてくれて。みんなのために懸命に頑張る姿ほど、尊いものはありません」
その言葉は、タエコ・グッドマンの胸を射た。彼女はハッとして、伸一の顔を見た。
「先生……」
何か言いかけたが、言葉にならなかった。しかし、彼女は、自分の心にわだかまっていた悶々とした思いが、霧が消えるように、にわかに晴れていくのを感じた。
タエコ・グッドマンが入会に踏み切った動機は、三年前に日本で母親が癌にかかり、医師から「六カ月の命」と宣告されたことであった。その苦悩のなかで、仏法の話を聞き、紹介者の指導通りに一心に信心に励んだ。そして、二カ月たって再検査を受けると、母親の癌の症状はすっかり消えていたのである。
その後、彼女は、職場で知り合ったアメリカ人と結婚し、渡米する。しかし、見知らぬ土地での生活は、日々、郷愁をつのらせた。彼女は、日本に帰れることを願って、真剣に信心に励んだ。入会するメンバーは二人、三人と増え、遂に十人を超えた。すると、彼女の心は揺らぎ始めたのである。
〝もし、自分が帰国してしまったら、後に残されたメンバーの面倒は、いったい誰がみるのだろうか……〟
日本に帰りたい一心で信心に励み、弘教に力を注いだことが、かえって、帰国をためらわせる結果となったのである。彼女の心は激しく揺れ動いた。それは、使命の目覚めといってよかった。
そんなさなかに、山本会長一行の訪米を知り、彼女はぜひ会長に会いたいと、一晩がかりで車を走らせてやって来たのだ。彼女は、「みんなのために懸命に頑張る姿ほど、尊いものはありません」という伸一の言葉を耳にした瞬間、感激とともに決意が込み上げた。
〝私は、このアメリカの地で頑張ろう。私を信頼して、信心を始めた同志のために……〟
人間性の光彩とは、利他の行動の輝きにある。人間は、友のため、人びとのために生きようとすることによって、初めて人間たりうるといっても過言ではない。そして、そこに、小さなエゴの殻を破り、自身の境涯を大きく広げ、磨き高めてゆく道がある。
<新・人間革命> 第1巻 錦秋 148頁~150頁
2021年10月19日
第1749回
会長就任の「覚悟」
<そして世界広布へ>
午後五時過ぎ、同行の幹部たちは、座談会に出かけていった。
外は雨になっていた。皆が出発すると、山本伸一はベッドの上に正座し、しばらく唱題を続けた。病魔との、真剣勝負ともいうべき闘いの祈りであった。伸一は唱題の後、ベッドで体を休めた。広宣流布の長途の旅路を行かねばならぬ自分の体が、かくも病弱であることが不甲斐なく、悔しかった。
伸一は、第三代会長として、一閻浮提広布への旅立ちをした、この年の五月三日の夜、妻の峯子と語り合ったことを思い出した。
──その日、夜更けて自宅に帰ると、峯子は食事のしたくをして待っていた。普段と変わらぬ質素な食卓であった。
「今日は、会長就任のお祝いのお赤飯かと思ったら、いつもと同じだね」
伸一が言うと、峯子は笑みを浮かべながらも、キッパリとした口調で語った。
「今日から、わが家には主人はいなくなったと思っています。今日は山本家のお葬式ですから、お赤飯は炊いておりません」
「確かにそうだね……」
伸一も微笑んだ。妻の健気な言葉を聞き、彼は一瞬、不憫に思ったが、その気概が嬉しかった。それが、どれほど彼を勇気づけたか計り知れない。
これからは子どもたちと遊んでやることも、一家の団欒も、ほとんどないにちがいない。妻にとっては、たまらなく寂しいことであるはずだ。だが、峯子は、決然として、広宣流布に生涯を捧げた会長・山本伸一の妻としての決意を披瀝して見せたのである。
伸一は、人並みの幸福など欲しなかった。ある意味で広布の犠牲となることを喜んで選んだのである。今、妻もまた、同じ思いでいることを知って、ありがたかった。
しかし、伸一は、それは自分たちだけでよいと思った。その分、同志の家庭に、安穏なる団欒の花咲くことを願い、皆が幸せを満喫することを望んだ。そのための自分の人生であると、彼は決めたのである。
峯子は、伸一に言った。
「お赤飯の用意はしておりませんが、あなたに何か、会長就任のお祝いの品を贈りたいと思っております。何がよろしいのかしら」
「それなら、旅行カバンがいい。一番大きな、丈夫なやつを頼むよ」
「カバンですか。でも、そんなに大きなカバンを持って、どこにお出かけになりますの」
「世界を回るんだよ。戸田先生に代わって」
峯子の瞳が光り、微笑が浮かんだ。
「いよいよ始まるんですね。世界広布の旅が」
彼は、ニッコリと笑って頷いた。
伸一は、もとより、広宣流布に命をなげうつ覚悟はできていた。広布の庭で戦い、散ってゆくことには、微塵の恐れも、悔いもなかった。もともと医師からも、三十歳まで生きられないと言われてきた体である。いつ倒れても不思議ではない。
しかし、恩師の志を受け継ぎ、世界広布の第一歩を踏み出したばかりで、倒れるわけにはいかなかった。伸一は今、シアトルのホテルでベッドに伏せながら、自らの体の弱さが悔しくてならなかった。
〝生きたい。先生との誓いを果たすために〟
彼は「南無妙法蓮華経は師子吼の如し・いかなる病さはりをなすべきや」(御書一一二四㌻)との御聖訓を思いつつ、熱に苛まれながら祈った。
激しさを増した雨が、ホテルの窓を叩いていた。
<新・人間革命> 第1巻 錦秋 156頁~160頁
2021年10月18日
第1748回
大切な仏子を不幸にさせてなるものか
十条は、座談会の様子を詳しく伝えた後、伸一に尋ねた。
「私たちとしては、一生懸命にやったつもりです。しかし、先生が出席された座談会とは、どこか雰囲気が違うのです。先生、この違いは、どこにあるのでしょうか」
伸一は静かに頷くと、強い語調で語り始めた。
「私も、何か特別なことをしているわけではない。ただ〝大切な仏子を不幸にさせてなるものか〟〝この人たちを幸せに導くチャンスは今しかない〟との思いでいつも戦っている。その一念が、皆の心を開いていく力になる。
わが子のことを常に思い、愛する母親は、泣き声一つで子どもが何を欲しているかがわかる。また、子どもは、その母の声を聞けば安心する。同じように、幹部に友を思う強い一念があれば、みんなが何を悩み、何を望んでいるのかもわかるし、心も通じ合うものだ。
そのうえで、何を、どう話せば、皆がよく理解できるのか、心から納得できるのか、さまざまな角度から考えていかねばならない。大事なことは、そうした努力を重ねていくことだ。私も、会合に臨む時には全力で準備にあたっている。考えに考え、工夫している。それが指導者の義務だからだよ。
幹部の話が、いつも同じで話題に乏しく、新鮮さもないというのは、参加者に対して失礼です。それは幹部が、惰性に流されている無責任な姿だ」
十条は、伸一の話を聞きながら、自分の姿勢を深く恥じた。
<新・人間革命> 第1巻 錦秋 162頁~163頁
2021年10月23日
第1753回
命限り有り
その帰りに、一行はシアトルの名所のワシントン湖に立ち寄った。この湖は、運河で海とつながり、湖と海には落差があるため、水位を調整する水門がつくられていた。その水門が閉じられ、船が運河を行く様子を眺めていると、しとしとと雨が降り始めた。
湖には、浮橋が架けられていた。一行は、この浮橋に立ってみた。湖面の彼方に、山々が雨で淡く霞み、黄や赤に染まった森の木々が水彩画のように見えた。
「本当にきれい! まるで絵のようね……。でも、この美しい葉も、すぐに散ってしまうと思うと、無常を感じるわね」
しんみりした口調で、清原かつが言った。伸一はそれに笑顔で応え、静かに語った。
「鮮やかな紅葉は、木々の葉が、限りある命の時間のなかで、自分を精いっぱいに燃やして生きようとする姿なのかもしれないね……。
すべては無常だ。人間も生老病死を避けることはできない。だからこそ、常住の法のもとに、一瞬一瞬を、色鮮やかに燃焼させながら、自らの使命に生き抜く以外にない。人生は、限りある時間との戦いなんだ。それゆえに、日蓮大聖人も『命限り有り惜む可からず遂に願う可きは仏国也』(御書九五五㌻)と明確に仰せになっている。今の私にほしいのは、その使命を果たすための時間なんだ……」
最後の言葉には、伸一の切実な思いが込められていた。しかし、その深い心を汲み取る人はいなかった。色づく錦秋の木々にも増して、伸一の心には、広宣流布への誓いが、鮮やかな紅の炎となって燃え盛っていた。
<新・人間革命> 第1巻 錦秋 163頁~164頁
2021年10月22日
第1752回
人種差別は
「人間革命」による以外に解決はない!
<他者支配のエゴイズムを
人類共存のヒューマニズムに転換>
山本伸一は、あの少年への仕打ちを目にして、人種差別の問題に深く思いをめぐらしていった。
──理不尽な差別を撤廃するうえで、〝黒人〟の公民権の獲得は不可欠な課題である。しかし、それだけで、人びとは幸せを獲得できるのだろうか。答えは「ノー」といわざるをえない。なぜなら、その根本的な要因は、人間の心に根差した偏見や蔑視にこそあるからだ。この差別意識の鉄鎖からの解放がない限り、差別は形を変え、より陰湿な方法で繰り返されるにちがいない。
人間は、人種、民族を超えて、本来、平等であるはずだ。その思想こそ〝独立宣言〟に表明されているアメリカの精神である。しかし、〝白人〟の〝黒人〟に対する優越意識と恐れが、それを許さないのだ。
問題は、
この人間の心をいかに変えてゆくかである。
それには「皆仏子」「皆宝塔」と、
万人の尊厳と平等を説く、
日蓮大聖人の仏法の人間観を、
一人ひとりの胸中に打ち立てることだ。
そして、
他者の支配を正当化するエゴイズムを、
人類共存のヒューマニズムへと転じゆく
生命の変革、すなわち、
人間革命による以外に解決はない。
伸一は、アメリカ社会の広宣流布の切実な意義を噛み締めていた。戸田城聖は生前、人類の共存をめざす自身の理念を「地球民族主義」と語っていたが、伸一は、その実現を胸深く誓いながら、心のなかで、あの少年に呼びかけていた。
〝君が本当に愛し、誇りに思える社会を、きっとつくるからね〟
<新・人間革命> 第1巻 錦秋 178頁~179頁
2025.2.8整理
2021年10月24日
第1754回
幸せはどこに?
一行は、午後には郊外を回った。辺りには、のどかな田園風景が広がっていた。
「この辺の農家の人たちの暮らしについて、いろいろ聞いてみたいね」
伸一は、ポツリと言った。
一軒の農家の前を通りかかると、そこに一人の若い婦人が立っていた。その家の主婦のようだ。正木永安が車を止めた。伸一は車を降りると、笑顔で婦人にあいさつした。
「ハロー」
その後を受けるように、正木が英語で話しかけた。
「こんにちは。シカゴの農家の暮らしについて、ちょっとお聞きしたいのですが……。こちらは、日本から来た創価学会の会長の山本伸一先生です。創価学会は世界の平和と人びとの幸福を実現しようとしている仏法の団体です」
正木は、こう言って伸一を紹介した。彼女は、快く正木の質問に答えて、シカゴの農家の生活や作物、また、家の歴史まで語ってくれた。一家は、ドイツから移住してきたという。
その話し声を聞いて、家のなかから、老婦人が外に出て来た。年齢は七十歳ぐらいであろうか。
「ウチのおばあちゃんです。きょうは、おばあちゃんの誕生日なんですよ」
若い婦人が伝えた。
それを聞くと、伸一は、
老婦人の手を取って言った。
「そうですか。おめでとうございます。
心からお祝い申し上げます。
どうか、いつまでも、いついつまでも
長生きしてください。
おばあちゃんが、元気でいることほど、
ご家族の皆さんにとって嬉しいことはありません。
それは一家の幸せにつながります。
また、ご家族は、
おばあちゃんを誰よりも大切にしてください。
その心が家族の愛情を強くし、
一家が末永く繁栄していく源泉になります。
幸せは、決して遠くにあるのではなく、
家庭のなかにあります」
正木が伸一の話を伝えた。老婦人は見知らぬ日本人の祝福に、嬉しそうに笑みを浮かべた。伸一は、微笑む老婦人を見て言った。
「それじゃあ、みんなでおばあちゃんの誕生日を祝って、バースデーソングを歌おう」
〽ハッピー・バースデー・トゥー・ユー……
<新・人間革命> 第1巻 錦秋 191頁~193頁
2025.2.8整理
慈光
2021年10月28日
第1761回
「聖教新聞を日本中、
世界中の人に読ませたい」
<人間の機関紙>
伸一は、かつて戸田城聖が、しばしば「聖教新聞を日本中、世界中の人に読ませたい」と語っていたことが、心に焼きついていた。その言葉を、必ず実現せねばならないと誓ってきた。そして、そのために、いかにして、聖教新聞を世界的な新聞に育て上げようかと、常に心を砕いていたのである。
秋月は、「はい」と答えたが、正直なところ、「世界一流の新聞」と聞いて、驚きと戸惑いを覚えた。聖教新聞は、この年の八月まで週刊八ページ建てであり、ようやく九月から水曜日四ページ、土曜日八ページの週二回刊になったばかりであった。
伸一は、聖教新聞の未来に、大いなる夢を馳せながら語った。
「聖教は学会の機関紙だが、私は、同時に、人間の機関紙という考え方をしているんだよ」
「人間の機関紙ですか」
「そう。人間の機関紙だよ。一般の新聞は、暗いニュースに満ちている。それは、社会の反映だから仕方がないにしても、
そうした社会のなかで、
人びとが、どうすれば希望を見いだしていけるのか、
歓喜をわき立たせていくことができるのかを考え、
編集している新聞はない。
また、人生の苦悩に対して、いかに挑み、
克服していくかを教えている新聞もない。
しかし、社会が最も必要としているのは、そういう新聞だ。
それをやっているのは、聖教新聞だけじゃないか。そう考えていけば、聖教新聞はまさに〝人間の機関紙〟という以外にないじゃないか」
秋月の顔が紅潮した。伸一は、グッと身を乗り出し、秋月を見つめて言った。
「秋月君、
聖教新聞の使命は極めて大きい。
学会にあっては、
信心の教科書であり、
同志と同志の心をつなぐ
絆になっていかなくてはならない。
また、社会にあっては、
不正、邪悪と戦い、
仏法の慈光をもって、
まことの人間の道を照らし、
万人に幸福と平和への道を
指し示していく使命がある。
軍部政府と命をかけて戦った、
牧口先生、戸田先生の精神を受け継ぐ
学会の機関紙以外に、
本当の平和の道は語れないからね」
<新・人間革命> 第1巻 慈光 245頁~246頁
2025.2.8整理
2021年10月29日
第1763回
大切な少年少女に、
正しい人間の生き方を教えたかった
<軍国主義と戦った『小学生日本』>
伸一は、戸田の姿を仰ぐように目を細めて、窓の外に視線を向け、そして、言った。
「戸田先生は、仏法者として弾圧を受けただけでなく、戦時中、雑誌の発行者としても、軍部政府と水面下で戦いを続けていたことを知っているかい」
「いいえ、知りませんでした」
「これは、戸田先生からお伺いしたことだが、先生は、昭和十五年(一九四〇年)の一月に、『小学生日本』という、少年少女向けの月刊誌を創刊されている。後に、私が編集長を務めた、『冒険少年』『少年日本』の前身ともいえる雑誌なんだ……」
戸田城聖が『小学生日本』を発刊したこの昭和十五年といえば、皇紀二千六百年の記念式典や奉祝行事が大々的に行われ、大政翼賛会が発足した年である。既に、日中全面戦争に突入してから二年半がたち、一九三八年(昭和十三年)には、国家総動員法が公布されていた。つまり、国を挙げての戦争への協力体制が、ますます強化されようとしていた時であった。尋常小学校の一年生から、「ススメ ススメ ヘイタイ ススメ」と書かれた教科書が使われ、軍国主義が幼い子どもたちの純白な心に、刷り込まれていった時代といってよい。
各種の雑誌も、競い合うようにして戦争を讃美していた。言論、思想も、政府の厳しい統制下に置かれていただけに、そうしなければ、何一つ出版することができなかったのである。また、新聞や雑誌の発刊に必要な紙も、極めて入手困難な状況にあった。まさに、自由なき、いまわしい暗黒の時代の到来を告げていた。
戸田は、未来を担う子どもたちが、軍国主義教育に歪められ、偏狭なものの見方、考え方に凝り固まっていくことを深刻に憂えた。
〝子どもたちは、他国の優れた文化や産業、国民性も知らぬままに育とうとしている。このまま排他性に染まり、国のために戦い、死ぬことのみを美徳とするようになれば、子どもたちの人生を狂わせてしまう。そうなれば、国の未来もまたあまりにも暗い〟
戸田は、一個の人間として、また仏法者の良心のうえからも、この事態を打開する何らかの戦いを開始しなければならないと考えた。そして、少年少女が世界に視野を広げ、物事の真実を見極める目を培える雑誌を発刊することを思い立ったのである。
しかし、そのころ、出版物への当局の統制は厳しさを増し、紙も不足していたところから、原則として、雑誌の創刊は認めないとの方針がとられていた。彼は、関係各所を駆け巡り、説得に努め、遂に『小学生日本』の創刊に成功したのである。
だが、もとより、国策に添った雑誌でなければならなかった。創刊号には、いかにも戦時下らしい、二、三の勇ましい題名が、目次に大きく刷られていたが、いずれも短編にすぎなかった。主流をなす連載は、極めて平和的な作品だった。しかも、創刊号にあった戦争に関係した二、三の企画は、しばらくすると姿を消し、『小学生日本』は、戦争讃美とはほど遠い、極めて異例な雑誌となった。
更に、特筆すべきは、広く世界に目を向け、諸外国の優れた文化、産業などを伝えるルポルタージュやヨーロッパの物語などが掲載されていたことである。また、戦争について扱った小説もあるが、驚くべきことには、戦争は決してお伽噺のように華々しいものではないと、登場人物に語らせている。
戦争を讃美しなければ、廃刊にされかねない時代のなかで、戸田はその編集方針を曲げなかった。彼は大切な少年少女に、正しい人間の生き方を教えたかったのである。
『小学生日本』は、やがて、尋常小学校が国民学校に改められたのに伴い、改題を余儀なくされた。当時、少年少女は、年少の国民の意味で〝小国民〟と呼ばれており、戸田はやむなく誌名を『小国民日本』と改めた。
彼が激動する時代のなかで、改題してもなお、少年少女向けの雑誌を発刊し続けたことは、後に続く小さき者を、力の限り、守り育てねばならぬという、決意の表明といえよう。
『小国民日本』に改題されて、最初の発刊となる昭和十六年の三月号には、「神秘と謎を解く」との特集が組まれた。そこに、戸田城聖は「科学の母」と題する、次のような巻頭言を執筆している。
「不思議や神秘なことがらに、驚きと畏れをもって礼拝したのは、未開で野蛮な古代の人であった。わからぬことをわからぬままに信じて、迷信に陥ったのは、科学する心のない中古時代の人達であった。
──☆──
なぜだろう。一体これは何だろう。という私達の心に起るさまざまの疑問を、正しくつきつめて行くところに、世の中を明るくし、世界を進歩発達させる科学の世界が開ける。
──☆──
ニュートンは、庭に林檎の落ちるのを見て万有引力を見出し、ワットは鉄瓶の湯の沸るのを眺めて蒸気機関を発明した。エヂソンもキューリーも、せんじつめれば、この疑問を正直にまっしぐらにつきつめた人々ではなかったか。
──☆──
「驚異と疑問こそ、科学の母である」
国家神道を支柱とした精神主義の色濃い時代に、
「わからぬことをわからぬままに」信ずる愚かさを、彼は少年少女に語りかけている。
そして、「疑問を正直にまっしぐらにつきつめ」、科学する心をもてというのである。
ここに、軍国時代の暗黒の潮流に対して、敢然と戦い挑む、戸田の良心の叫びを聞く思いがしてならない。
更に『小国民日本』(国民学校上級生)の十月号には、「護れ大空」と題する特集が組まれている。その勇壮なタイトルとは裏腹に、そこには、防空マスクや防空壕のつくり方など、いかにして子どもたちが自分の身を守ればよいかが、詳述されている。また、そのなかには、イギリスやソ連の子どもたちの防空訓練に触れた寄稿もある。そこには、こう記されている。
「特にイギリスの小国民は、どれほどつらい、苦しい空襲を受けて来ているか、わたし達が考える以上に悲しいものであることは、たびたびニュースで伝えられています。
最初は空襲の恐しさにお父さんやお母さんと別れ別れになってアメリカに避難したり、田舎に離れて行ったりしました。
……(中略)……危ない都会にいる子どもも少なくありませんが、爆弾が遠くにでも落ちると見ると、速ぐに道路に伏せをして身の危険を守っていますが、その様子はすっかりなれて落着いたものだということであります」
この号の発行日は「昭和十六年(一九四一年)十月一日」とあり、それは、日本が米英に、宣戦を布告する、わずか二カ月ほど前にすぎない。このころ、既に日英両国の関係はこじれ、イギリスを敵性国とする見方が強まっていた。そのなかで、イギリスの子どもたちが空襲に苦しめられ、健気に身を守っているという状況を同情的に記した一文を掲載することは、決して容易なこととは思えない。
戸田城聖には、日本の子どもに限らず、世界中の子どもたちが、守るべき対象であるとの認識があった。また、〝子どもたち同士が、憎み合う必要などまったくない。むしろ、その苦しみを知り、手を結びあうべきである〟との、明確な主張があった。つまり、特集のタイトルこそ、「護れ大空」であったが、彼が守ろうとしたものは、日本の大空よりも、次代を担う少年少女の尊い命であったのだ。この企画のなかにも、〝生きよ、生きてくれ〟と、必死に若い魂に語りかけようとする、戸田の思いを汲み取ることができよう。
『小国民日本』は、やがて『少国民日本』に改題され、一九四二年(昭和十七年)四月ごろに廃刊となる。ますます厳しくなる統制下で、当局の意図通りに戦争を讃美し、死に急ぐことを煽り立てる雑誌を作ることより、廃刊の道を彼は選んだのかもしれない。戦後、日本のジャーナリズムは、ことごとく平和主義に転じた。言論、出版の自由が保障された世の中で、平和を叫ぶことは容易である。しかし、それが仮面の平和主義であるか、本物であるかを見極めるには、あの戦時中に、何をなしたかを問わねばならない。これは、ジャーナリズムに限らず、宗教についてもいえる。今日、いかに平和や民主を叫び、正義の仮面を被ろうが、戦時中の在り方のなかに、その教団の正体があることを見過ごしてはなるまい。
<新・人間革命> 第1巻 慈光 246頁~253頁
2021年10月28日
第1762回
聖教新聞は
『世界一流』の新聞に!
<一騎当千の記者>
「戸田先生は、あの時代のなかで、ジャーナリストとして、ギリギリのところで戦われた。それこそ、聖教新聞が受け継がなくてはならない精神なんだよ。信念も哲学ももたない言論は、煙のようにはかないものだ。しかし、聖教新聞には、仏法という大生命哲理がある」
秋月は、緊張した顔で、伸一の話に、じっと耳を傾けていた。ホテルの窓に、木漏れ水がキラキラと映えていた。
秋月が尋ねた。眼鏡の奥の彼の目は、燃え輝いていた。
「山本先生、聖教新聞が世界一流の新聞になるために、記事を書くうえで、最も心すべき点は、なんでしょうか」
「まず、機関紙として、
同志が確信と自信をもち、勇気がわくという記事を心がけるのは当然です。
そのうえで、根本的には大仏法の慈悲の精神をもとに、世界の平和、人類の幸福の追求をめざすことだよ。
国の利害やイデオロギーによるのではなく、地球民族、地球家族として、ともに人間の道を探り、創ろうという主張が大事になってくる。
私は、聖教新聞を、『世界の良心』『世界の良識』といわれるような新聞にしなくてはならないと、かねがね思っている。これこそ、本来の大仏法の精神であるからだ」
秋月は、自分の発想の殻を、大きく打ち破られた思いがした。彼は彼なりに、紙面の在り方を考えてはいたが、そこまで考えたことはなかった。
「そのうえで大切なことは、
一切衆生が皆平等という仏法の普遍的な哲理を、いかにわかりやすく、社会的に、現代的に、そして斬新に表現することができるかだ。
つまり、万人にわかる開かれた言葉で、仏法を語ることだよ。学会員にしかわからない新聞では、社会には広がらない。
まして会員でさえ理解できないような難解な新聞になったら、編集者の自己満足になってしまう。
それから、社会が何を求め、何を必要としているかを、的確に見抜いていくことだ。
仏法にも、学会の現実の姿のなかにも、社会が欲する、すべての解答が用意されている。それを、社会、時代のテーマに即して、常に示していけるかどうかだ。
そして、日々革新だよ。時代も動いている。社会も動いている。人間の心も動いている。それに敏感に反応しながら、触発と共感の指標を提示し続けることだね。
だから、見出しにせよ、記事にせよ、あるいは割り付けにしても、過去のものを踏襲して、それに安住しているようではいけない。
新聞は生き物といってよい。鮮度の悪い魚は見向きもされないように、惰性に陥り、マンネリ化した新聞は、読者から見捨てられてしまうものだ」
それは、明快にして要を得た指導であった。耳を傾ける秋月の顔には、次第に明るさが増していった。
「秋月君、紙面を刷新していくには、結局は、記者の一念を刷新していくしかないんだよ。挑戦の気概を忘れ、惰性化し、努力も工夫もなく、受け身で仕事をするような記者では、何千人、何万人いようが、とても、世界の新聞とは、太刀打ちすることなどできない。必要なのは、全学会を背負って立ち、ペンをもって世界を変えようとする、師子のような、一騎当千の記者だ。そうした記者が、五人か十人もいれば十分だよ。本当の言論戦は、数ではないからな。世界一流の新聞ということは、世界一流の記者をつくるということなんだ。育てようよ、本物の記者を。広宣流布の戦いというのは、言論戦なんだから」
聖教新聞は、編集部長である秋月の双肩にかかっていたといってよい。彼は青年部長として活動の中核を担いながら、毎号の新聞の発行に全力投球していた。この海外訪問でも、同行の幹部の一人として、メンバーの指導、激励にあたりながら、自ら写真を撮り、明け方近くまでかかって原稿を書き、それを本社に郵送していた。そのなかで、山本伸一を会長に迎えて新しい時代の幕が開かれた今、聖教新聞の未来は、いかにあるべきかを考え続けていた。しかし、霧がかかったように、明確な展望を見いだすことはできなかった。
そんな秋月の気持ちを察して、山本伸一は、この日、聖教新聞について語り合ったのである。彼は、更に希望の未来図を語っていった。
「やがて、十年か十五年もすれば、海外にも、聖教新聞の特派員や駐在員を、どんどん出すようになるだろうね。そして、聖教の記者が、各国の大統領や識者にインタビューしながら、仏法の平和思想を堂々と論じていくことが日常茶飯事になる時代が必ず来る。また、世界中の各界を代表する指導者が、どんどん聖教に原稿を書き、ともに恒久平和への道を探求するようにしようじゃないか。そうなれば面白いぞ」
<新・人間革命> 第1巻 慈光 254頁~257頁
開拓者
2021年11月4日
第1770回
人間の心を打つものは、
「誠実」なる行動以外にない
その夜、一行は旅行会社を通して予約しておいたホテルに移り、そこで支部結成のための打ち合わせを行った。各地に点在するメンバーの数を割り出し、どこに地区をつくるか、誰を中心者にするのか、綿密な検討がなされた。
打ち合わせが終わったのは深夜だった。伸一の肉体の疲れは既に限界を超え、目まいさえ覚えた。しかし、バッグから便箋を取り出すと、机に向かい、ペンを走らせた。日本の同志への激励の便りであった。手紙は何通にも及んだ。
彼は憔悴の極みにあったが、心には、恩師・戸田城聖に代わってブラジルの大地を踏み、広布の開拓のクワを振るう喜びが脈動していた。その歓喜と闘魂が、広宣流布を呼びかける、熱情の叫びとなってあふれ、ペンは便箋の上を走った。
ある支部長には、こうつづっている。
「今、私の心は、わが身を捨てても、戸田先生の遺志を受け継ぎ、広布の総仕上げをなそうとの思いでいっぱいです。そのために大事なのは人です、大人材です。どうか、大兄も、私とともに、最後まで勇敢に、使命の道を歩まれんことを切望いたします。そして、なにとぞ、私に代わって支部の全同志を心から愛し、幸福に導きゆかれんことを願うものです」
日本の同志は、この時、伸一が、いかなる状況のなかで手紙を記していたかを、知る由もなかった。しかし、後日、それを知った友は、感涙にむせび、拳を振るわせ、共戦の誓いを新たにするのであった。人間の心を打つものは、誠実なる行動以外にない。
<新・人間革命> 第1巻 開拓者 290頁~291頁
2021年10月25日
第1756回
仕事は真剣勝負
祈りは誓願
逆境は仏法証明のチャンス
<仏法は最高の道理>
伸一は、ここでは、多くの時間を質問会に当てた。農業移住者としてブラジルに渡り、柱と頼む幹部も、相談相手もなく、必死で活路を見いだそうとしている友に、適切な指導と励ましの手を差し伸べたかったのである。
「どうぞ、自由に、なんでも聞いてください。私はそのために来たんです」
彼が言うと、即座に四、五人の手があがった。皆、こうした機会を待ち望んでいたのである。質問の多くは、生き抜くための切実な問題だった。
四十過ぎの一人の壮年が、兵士のような口調で、緊張して語り始めた。 「自分の仕事は農業であります!」
「どうぞ気楽に。ここは、軍隊ではありませんから。みんな同志であり、家族なんですから、自宅でくつろいでいるような気持ちでいいんです」
笑いが弾けた。日焼けした壮年の顔にも、屈託のない笑みが浮かんだ。
この壮年の質問は、新たに始めた野菜づくりに失敗し、借金が膨らんでしまったが、どうすれば打開できるかというものだった。
伸一は聞いた。
「不作になってしまった原因はなんですか」
「気候のせいであったように思いますが……」
「同じ野菜を栽培して、成功した方はいますか」
「ええ、います。でも、たいていの人が不作です」
「肥料に問題はありませんか」
「……詳しくはわかりません」
「手入れの仕方には、問題はありませんか」
「…………」 「土壌と品種との関係はどうですか」
「さあ……」
壮年は、伸一の問いに、ほとんど満足に答えることができなかった。
〝この人は自分なりに、
一生懸命に働いてきたにちがいない。
しかし、誰もが一生懸命なのだ。
それだけで良しとしているところに、
「甘さ」があることに気づいていない〟
伸一は、力強く語り始めた。
「まず、同じ失敗を繰り返さないためには、
なぜ、不作に終わってしまったのか、
原因を徹底して究明していくことです。
成功した人の話を聞き、
参考にするのもよいでしょう。
そして、
失敗しないための十分な対策を立てることです。
真剣勝負の人には、常に研究と工夫がある。
それを怠れば成功はない。
信心をしていれば、
自分の畑だけが、
自然に豊作になるなどと思ったら大間違いです。
仏法というのは、最高の道理なんです。
ゆえに、
信心の強盛さは、人一倍、研究し、工夫し、
努力する姿となって表れなければなりません。
そして、
その挑戦のエネルギーを
湧き出させる源泉が真剣な唱題です。
それも”誓願”の唱題でなければならない」
「セイガンですか……」
壮年が尋ねた。
皆、初めて耳にする言葉であった。
伸一が答えた。
「”誓願”というのは、
自ら誓いを立てて、
願っていくことです。
祈りといっても、
自らの努力を怠り、
ただ、棚からボタモチが落ちてくることを
願うような祈りもあります。
それで良しとする宗教なら、
人間をだめにしてしまう宗教です。
日蓮仏法の祈りは、
本来、”誓願”の唱題なんです。
その”誓願”の根本は広宣流布です。
つまり、
”私は、このブラジルの広宣流布をしてまいります。
そのために、
仕事でも必ず見事な実証を示してまいります。
どうか、最大の力を発揮できるようにしてください”
という決意の唱題です。
これが私たちの本来の祈りです。
そのうえで、
日々、自分のなすべき
具体的な目標を明確に定めて、
一つ一つの成就を祈り、
挑戦していくことです。
その真剣な一念から、
智慧が湧き、
創意工夫が生まれ、
そこに成功があるんです。
つまり、『決意』と『祈り』、
そして『努力』と『工夫』が揃ってこそ、
人生の勝利があります。
一攫千金を夢見て、
一山当てようとしたり、
うまい儲け話を期待するのは間違いです。
それは、信心ではありません。
それでは観念です。
仕事は生活を支える基盤です。
その仕事で勝利の実証を示さなければ、
信心即生活の原理を立証することはできない。
どうか、安易な姿勢はいっさい排して、
もう一度、新しい決意で、
全力を傾けて仕事に取り組んでください」
「はい。頑張ります」
壮年の目には、
決意がみなぎっていた。
伸一は、
農業移住者の置かれた厳しい立場をよく知っていた。
そのなかで
成功を収めるためには、
何よりも自己の安易さと
戦わなくてはならない。
敵はわが内にある。
逆境であればあるほど、
人生の勝負の時と決めて、
挑戦し抜いていくことである。
そこに御本尊の功力が現れるのだ。
ゆえに逆境はまた、
仏法の力の証明のチャンスといえる。
<新・人間革命> 第1巻 開拓者 292頁~296頁
2025.2.8整理
2021年11月3日
第1769回
学会は指導主義
<その人の幸せを祈る>
壮年の一人が、伸一に尋ねた。
「私には、人に信心を教えるような経験も、実力もありません。これから、支部の幹部として、みんなから相談をもちかけられた場合、どうすればよいでしょうか」
真摯な質問であった。伸一は微笑んだ。
「経験は、これから積めばいいんです。学会は指導主義です。指導は、教授とは違う。自分が習得したものを人に教えるのが教授ですが、指導というのは、進むべき道を指し示し、ともに進んでいくことです。したがって、御書にはこう仰せである、学会ではこう教えていると、語っていけばいいんです。そして、一緒に、その人の幸せを祈ってあげることです。これは、誰にでもできることだが、人間として最も尊い行為です。自分のために、祈ってくれる同志がいるということほど、心強いことはありません。それが、最大の力になり、激励になります。また、これからアメリカには、日本から幹部を派遣しますから、わからないことは、その人に率直に聞いてください。リーダーとして、大切なことは求道心です」
伸一は、幹部の基本を、諄々と話していった。
<新・人間革命> 第1巻 開拓者 336頁
 日めくり人間革命
日めくり人間革命